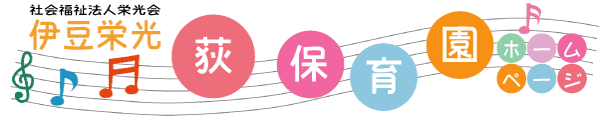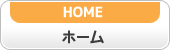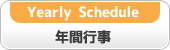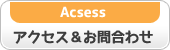苦情解決
伊豆栄光荻保育園では、日々皆様から頂戴したご意見やご要望あるいは苦情を真摯に受け止め、その解決を図りながら、保育園に在園する子ども達と保護者の皆様にとってより良い保育園運営を目指しております。
頂戴したご意見やご要望を適切に保育園の運営に反映するために、社会福祉法82条の規定に基づき『苦情処理マニュアル』を定め、苦情解決機関、及びそれに関わる苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員を設置し、サービスの向上を図っております。
事業内容
1.苦情解決窓口
苦情解決責任者 ... 山本 貴美子(園長)
第三者委員 ... 鳥居康子(元議員)、横山欣正(元荻区長)
2.苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員にも直接苦情を申し出ることもできます。
3.苦情の受付報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告致します。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
4.苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人との誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち合いを求めることができます。
5.解決結果の公表
サービス向上や信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き事業報告書や、湯川保育園の理事や当ホームページ等に記載し、公表致します。
★保護者の皆様には、保育園を利用するにあたってお気づきの点はご遠慮なく上記のシステムをご活用ください。 苦情申出については、直接保育園、または第三者委員にご連絡ください。
苦情解決報告
令和7年度
10月:なし
7月:なし
6月:一件
園外保育の排泄対応に関するご報告と再発防止について
【事実】
令和6年3月の園外保育の昼食前に、和式トイレを使用した園児の衣服が排泄により濡れてしまいました。
職員は「後で着替えよう」と声かけしましたが、その後イベント準備の役割を優先して、着替えの対応を失念しました。
園に戻っても着替えの支援を行わないまま、園児本人が自力で着替え、そのまま降園となり、保護者の方からの連絡帳を通じて今回の事が判明しました。
【不適切保育とのご指摘】
保護者の方より
・濡れた状態で昼食前から帰園するまで過ごさせた不衛生さ
・こどもの不快感や心の状態への無配慮
・園外保育を行う上での職員体制・意識の問題について
【これまでの仕組み】
・排泄後の着替えは必要に応じてその都度行う基本の対応をしていました。
・園外保育時は職員で役割を柔軟に分担しながら活動を進めていました。
・保護者への報告もその都度行っており、基本的に大きな漏れはありませんでした。
【園としての受け止め】
今回のことは保育園の仕組みや職員の意識等、いくつかの問題が合わさり発生した重大な事案であり園としての不適切な保育であったと受け止めております。
【問題点】
・園外保育という環境のもとで、職員個人の記録と判断に頼ったことで対応の記録と引き続きがなされなかったこと。
・こどもの訴えに対して着替えの対応もなされず、保育者としてこどもに寄り添う気持ちが欠けてしまったこと。
・こどもの安全と心身の快適さよりも自分の役割を優先してしまったこと。
・個人に任された役割が大きく、不測の事態が起こった時に、一人で臨機応変な対応をとることができなかったこと。また、各自が自分以外の職員の役割や動きについて理解していなかったこと。
【今後の仕組みによる再発防止策】
・園外保育中も含めて、排泄や着替えが必要な場面は必ず記録し、引き継ぎ・確認を徹底します。
・保護者への報告事項は、連絡帳・記録表、新たに園外保育でも使用できるチェックリストを作成、活用し、帰園後は口頭伝達の漏れがないようにします。
・職員は、自分の役割を各自持ちながらも、その日の全体活動が見える細かい打ち合わせをし、活動を進めていきます。
【こどもへの寄り添う気持ちを大切にした保育に向けて】
・日々の保育の中で、こどもの思い・願いを軽視することなく、こどもの変化に気付けること、気持ちに寄り添い思いを大切にしたかかわりをより大事にしていきます。
保護者の皆様には深くお詫び申し上げるとともに今後もお子さまの健やかな成長を支える保育の質向上に全力で取り組んでまいります。
4月:なし
令和6年度
4月:なし
7月:なし
10月:なし
1月:なし
令和5年度
4月:なし
7月:一件
<苦情内容>
7月中旬、五歳児の習字の進め方に対する苦情がありました。
(自己肯定感を下げるようなことなく、子供の意欲をもっと引き出せるように…等)
翌日職員で話し合い、以下の対応を提案し納得していたきました。
<対応内容>
・五歳児保育は、主に進める職員1名、フォローする職員1名と二名体制で行っていく。
・習字に関しては、道具、筆の使い方を知り、線・はね・とめ・はらいなど基礎的なことを知る。
後半から書きたい文字を園児が決め、自分の力で書く楽しさを味わえるようにする。
・書く枚数を4枚と決め、その中から自分の一枚を選び、掲示していく。
・ひとりひとりの意欲・好奇心を大切にしていく。
10月:なし
1月:なし
令和4年度
4月:なし
7月:なし
10月:なし
1月:なし
令和3年度
4月:なし
7月:なし
10月:なし
1月:なし